
出典:X
芦田愛菜さんの両親はどんな人?
テレビで見るたびに、「この子、どうしてこんなに落ち着いてるの?」と感じたことはありませんか?
芦田愛菜さんは、子役として一世を風靡しただけでなく、現在は慶應義塾大学に進学し、女優としてもインテリとしても注目されています。
その賢さや丁寧な話し方、人への気遣いのある立ち振る舞いを見て、
「きっと、親御さんの教育がすごいんだろうな…」
と、ふと気になったことのある方も多いはず。
今回は「芦田愛菜 両親」というキーワードから、彼女を育てたご両親の教育方針や人物像、家庭の環境について深掘りしていきます。
芦田愛菜のプロフィール

出典:X
氏名:芦田 愛菜(あしだ まな)
-
生年月日:2004年6月23日
-
出身地:兵庫県西宮市
-
血液型:A型
-
身長:150cm
-
職業:女優、タレント、歌手、声優、ナレーター
-
所属事務所:ジョビィキッズプロダクション
-
主な出演作品:
-
テレビドラマ:
-
『Mother』(2010年、日本テレビ)道木怜南役
-
『マルモのおきて』(2011年、フジテレビ)笹倉薫役
-
『明日、ママがいない』(2014年、日本テレビ)
-
『OUR HOUSE』(2016年、フジテレビ)
-
『最高の教師』(2023年)
-
-
映画:
-
『ゴースト もういちど抱きしめたい』(2010年)
-
『うさぎドロップ』(2011年)
-
『パシフィック・リム』(2013年)
-
『星の子』(2020年)
-
『メタモルフォーゼの縁側』(2022年)
-
-
-
受賞歴:
-
『第34回日本アカデミー賞』新人俳優賞(2011年)
-
『第54回ブルーリボン賞』新人賞(2011年)
-
-
特技:スイミング、ピアノ、ダンス
-
趣味:読書
-
学歴:
-
慶應義塾中等部卒業
-
慶應義塾女子高等学校卒業
-
慶應義塾大学在学中
-
芦田愛菜さんは、3歳で芸能界入りし、子役として数々の作品に出演。特に、2010年のドラマ『Mother』で注目を集め、以降、多方面で活躍を続けています。
そもそも、芦田愛菜さんの両親はどんな人?

出典:X
父親は一部上場企業のエリートビジネスマン
芦田さんの父・芦田博文さん(報道による仮名)は、三井住友銀行の幹部社員として知られており、現在も金融関係の重要なポジションにいると言われています。
社内でも高く評価される人望のある人物で、「きっちりとした躾をする一方、娘の意思を尊重するタイプ」だと関係者は話しています。
母親は“教育ママ”ではなく、“見守るママ”
一方、母親は専業主婦として芦田さんを育てながらも、過干渉にならず、本人の自主性を大事にしてきたといわれています。
特に印象的なのが、あるインタビューで芦田さん自身が語ったこの一言:
「勉強しなさいと言われたことが、一度もないんです。」
この言葉からも、ご両親がいかに信頼して見守ってきたかがわかります。
教育方針のポイントは「自分で考えさせる」

出典:X
両親は、「答えを与えるのではなく、自分で考えさせる」ことを何よりも大事にしていたそうです。
たとえば、
-
毎晩の読み聞かせ(0歳〜10歳まで続いた)
-
疑問に感じたことを一緒に辞書や図鑑で調べる習慣
-
たとえ失敗しても、叱るのではなく“気づきを促す”声かけ
など、家庭の中に自然に学びの時間が組み込まれていました。
これは、まさに“家庭が学びの場”だったということ。
私自身も、読書好きの親に育てられた身として、芦田さんの家庭スタイルには強く共感します。 「教育って、日常の中に溶け込ませるのが一番なんだ」と、あらためて考えさせられました。
塾なし・ゲームなしでも成績はトップレベル?

出典:Instagram
意外かもしれませんが、芦田さんは小学校時代、塾に通わず家庭学習だけで慶應義塾中等部に合格しています。
また、テレビ番組で「家にゲームはない」と語っており、その分、
-
読書
-
ピアノ
-
水泳
-
博物館や展覧会に行く習慣
など、知的好奇心を育てる時間にあてていたそうです。
ここでも両親の「体験を重ねる教育」の姿勢が光ります。
両親の影響で育まれた“人間力”の正体
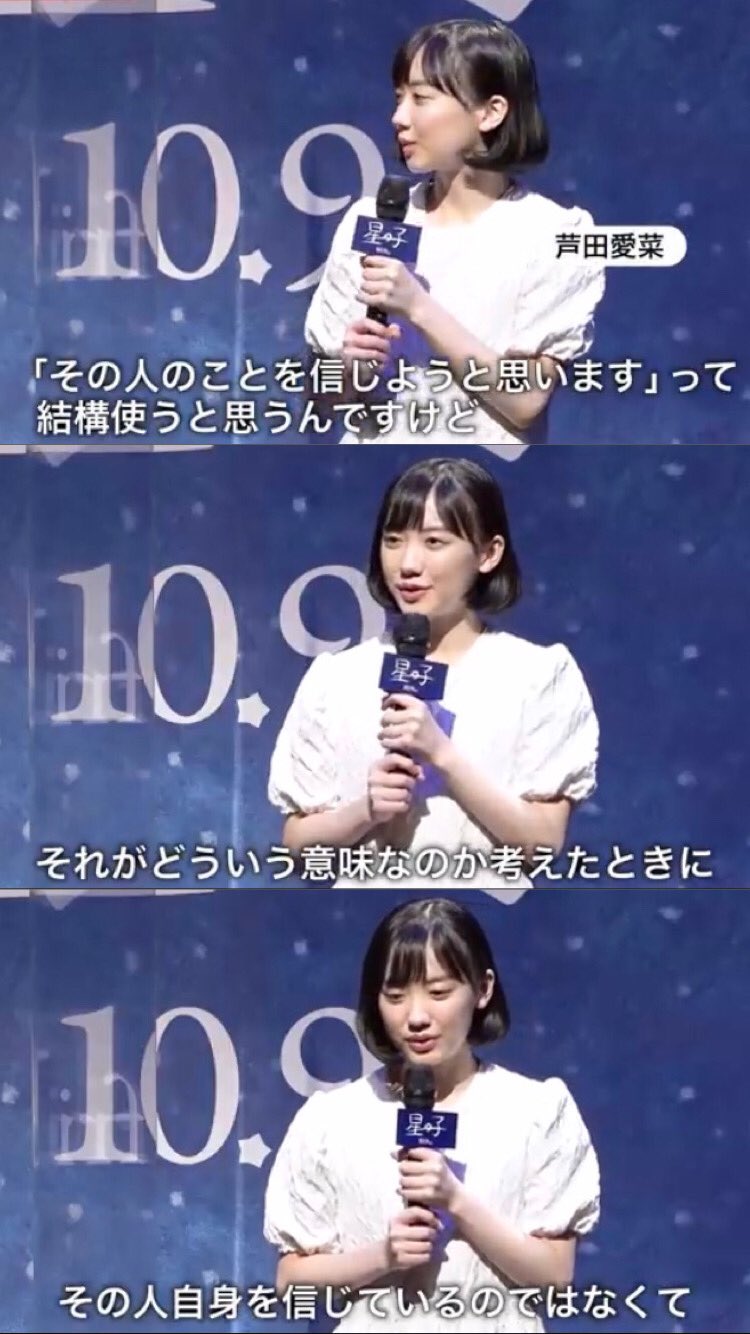
出典;X
芦田さんの魅力は、ただ“頭がいい”というだけではありません。
-
誰に対しても丁寧な言葉遣い
-
大人びた考えを持ちながら、押し付けがましくない
-
自分の意見を持ちながら、他人の立場も想像できる
こうした“人間力”は、家庭での対話や経験から自然と身についたものだと感じます。
つまり、芦田さんの賢さは、ご両親が「信じて見守る」を貫いた教育の賜物なのです。
「何かを教える」より、「どう育つかを信じる」こと
芦田愛菜さんのように、芯のある優しさや知性をもった子どもに育ってほしい。
そう願う方にとって、ご両親のスタンスや家庭の過ごし方は、たくさんのヒントになるはずです。
「教育って、こうしなきゃ」と思い込む前に、
まずは“信じて見守る”ことから始めてみませんか?





![星の子 [ 芦田愛菜 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/9069/4907953219069.jpg)
![まなの本棚 [ 芦田 愛菜 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/7007/9784093887007_1_3.jpg)
コメント